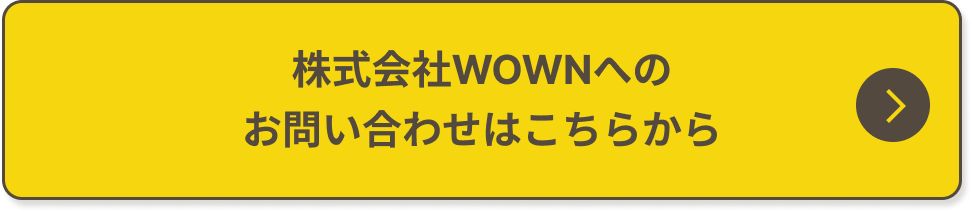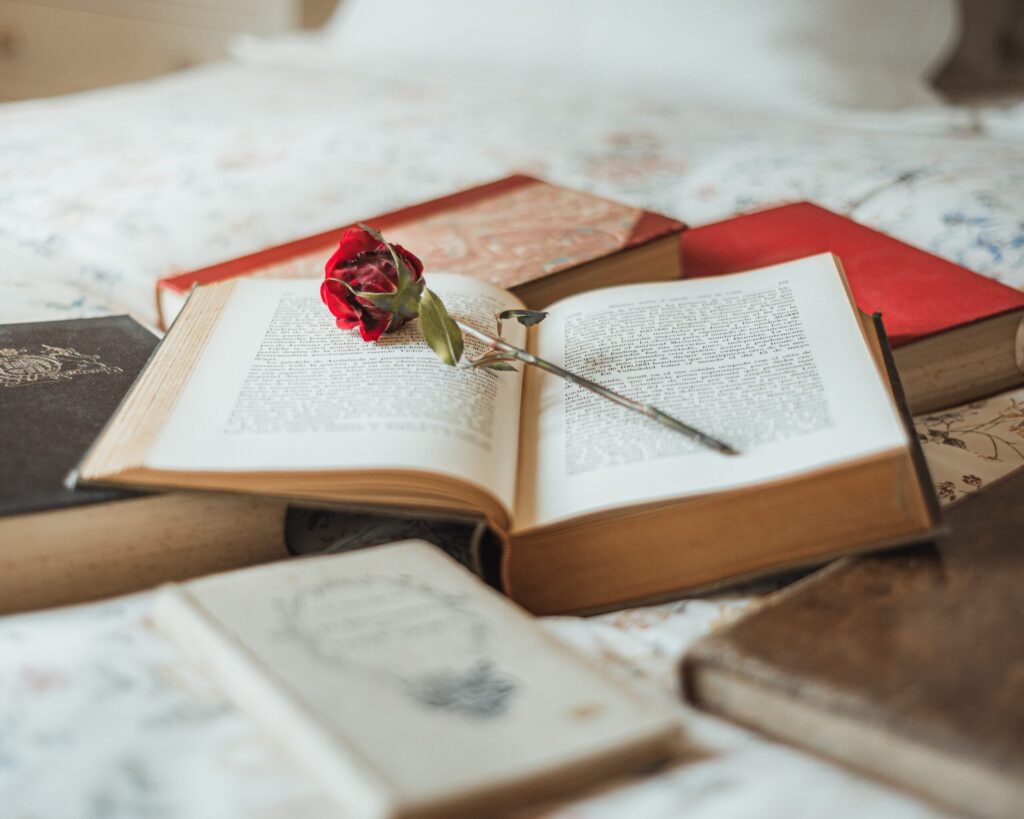
商品を選ぶとき、あなたは何を重視しますか?
価格でしょうか、それとも機能でしょうか?
もちろん、それらも大切です。
ですが今、購買を左右する大きな要因として注目されているのが、「ブランドへの共感」です。
ブランドのポリシーやストーリーに共感できるか──つまり、「推したくなるブランド」であるかどうかが、重要な判断基準になりつつあるのです。
本記事では、そんな“推されるブランド”になるために欠かせないストーリーブランディング戦略を、成功事例とともに紹介します。
目次
ストーリーブランディングとは?
いまの消費者は、単に「モノ」を買うのではなく、「意味」や「姿勢」に共感してブランドを選ぶようになっています。
そうした中で注目されているのが「ストーリーブランディング」。
これは、ブランドに“人格”を与え、物語を通じて共感を呼び、最終的に共鳴を生み出すマーケティング手法です。
商品のスペックや価格ではなく、そこに込められた想いや背景、世界観が、消費者の心を動かします。
ストーリーブランディングのポイント
- ブランドに“人格”を宿らせることで、消費者との感情的なつながりを生む
- 創業の想いや開発背景など、ブランドの内側にあるストーリーを可視化する
- 一貫した価値観や世界観で、ブランドの「らしさ」を築きあげる
- ファンが語りたくなるストーリー設計を意識することで、自然な拡散が起こる
パタゴニア:思想で選ばれるブランドの代表格
アウトドアブランド・パタゴニアは、デザイン性や機能性の高さもさることながら、「環境保護活動に全力で取り組む企業姿勢」に共鳴するファンを獲得しています。
創業者イヴォン・シュイナードはクライマーであり、自然との共生を重視する生き方を体現してきました。
その思想は企業にも浸透し、魚網を衣料品にリサイクルしたり、ウールやコットンに再生素材を活用したり、製造工程での水使用量を徹底的に削減したりと、あらゆる面で環境保護を重視しています。
売上の1%を地球環境保護に寄付するほか、古くなった製品は修理して使い続けることを推奨しており、子ども服はお下がりを受け継いで使おうというキャンペーンも展開。
さらに、売れ残った製品も短期的かつ極端な値下げ販売を行うのではなく、ウェブアウトレットで適正価格を維持しながら売り切るまで販売を続け、商品の廃棄を一切しないという徹底ぶりです(実際、アウトレット価格でも人気製品は即完売するほどです)。
「長く使うこと」が美徳という姿勢を一貫して示し続けるこのブランドには、モノを売る企業というより、思想を持った一人の人格が宿っているような印象さえ受けます。
価格は決して安くありませんが、「このブランドの姿勢に共感しているからこそ買う」というファンが多く、まさにストーリーブランディングが成功している好例です。
パタゴニアのストーリーが持つ“人格”
- 環境保護を第一に考える“活動家”タイプの人格
- モノを売るのではなく、消費スタイルを変える思想家としての一面
- リサイクル素材の使用を追求し、肌触りを多少犠牲にしてでも環境保護を優先する姿勢──「買わないで」という逆説的メッセージに象徴される、徹底した環境第一主義
- 長く使うこと、廃棄しないことを勧める“誠実で信念のある語り手”
上羽絵惣:老舗絵具店がネイルで蘇る
1751年創業の上羽絵惣株式会社は、日本最古の絵具メーカー。
270余年にわたって日本画用の絵具を製造してきた同社ですが、日本画市場の縮小に伴い、経営難に直面したことがあります。
そんな同社が起死回生をかけて開発したのが、伝統素材「胡粉(ホタテ貝の粉)」を活かした水性ネイル「胡粉ネイル」。有機溶剤を使用せず、刺激臭がなく速乾性も高いため、子どもや高齢者、敏感肌や病気療養中の人まで安心して使えるプロダクトです。
実際、「抗がん剤治療の副作用で爪が変色してしまったが、このネイルのおかげで外出時におしゃれを楽しめるようになった」といった声も寄せられており、見た目をカバーするだけでなく、安心して使える点が高く評価されています。
さらに注目すべきは、日本画の伝統色を再現したカラーバリエーション。
繊細で奥行きのある色味はファッション性にも優れ、色名には「薄紅(うすくれない)」「藍白(あいじろ)」「蘇芳(すおう)」など、情景や感情を想起させるような名が冠されています。
それぞれの色に物語が込められており、選ぶ楽しさとともに“日本の美”を指先で楽しむという体験価値をも提供。
最近では男性向けの胡粉ネイルも展開し、ネイルのジェンダーレス化にも柔軟に対応しています。
伝統と現代の感性が融合したブランドとして、上羽絵惣はまさに“応援したくなる企業”の理想形を体現しています。
また、胡粉ネイルの人気をきっかけに、もともとの事業である絵具にも改めて注目が集まるという好循環も生まれました。
実際、「胡粉ってそういう素材なんだ」「こんなふうに使えるなんて知らなかった」と驚く声も多く、ネイルを通じて伝統素材そのものに新たな関心が寄せられています。
日本画を描くとまではいかなくても、「日本の絵具ってこんなに美しい色なんだ」「伝統色って面白い」と感じる人が増えており、同社の発信が日本の色文化そのものへの関心を呼び起こしているのです。
上羽絵惣のストーリーが持つ“人格”
- 伝統と革新の橋渡し役となる“文化の語り部”
- 爪や肌へのやさしさを追求する“気遣い上手な繊細派”
- 絵具屋という原点を忘れず、色に物語を込める“情緒豊かなクリエイター”
- 誰もがネイルを楽しめる社会を目指す“共感力のある挑戦者”
中小企業がストーリーブランディングを実践するには?
ストーリーブランディングは、大企業に限ったものではありません。
むしろ、規模が小さいからこそ、「人の顔が見える物語」や「創業者の想い」がリアルに届きやすいという利点があります。
中小企業が取り組むべきポイントは、以下の通りです:
- 商品やサービスに込めた想いを、飾らず自分の言葉で語る
- 創業エピソードや転機となった出来事を開示する
- 顧客の声を巻き込み、一緒にストーリーをつくる
- 自社の価値観や信念を、発信するすべてに一貫させる
- 一つひとつの製品が「ブランドの物語の一部」として語られるようにする
大切なのは、物語を「演出する」ことではなく、実直に「語る」こと。
企業のリアルな姿にこそ、ファンは共感を寄せます。
事例から読み解く“推しポイント”
パタゴニアの推しポイント:
商品を売るより、長く使う文化を広める思想に共感。企業活動そのものがサステナブルなストーリーになっている。
上羽絵惣の推しポイント:
老舗絵具店が伝統素材を活かして異業種に挑戦。やさしさと文化性が融合した“使う人に寄り添うストーリー”が響く。
どちらの企業も、製品を通じて「何を伝えたいのか」が明確で、かつ行動でも裏付けされている点が共通しています。
まとめ
“推したくなるブランド”とは、商品のスペックや価格とは異なる次元の、人の心に寄り添える存在です。
その背景には、丁寧に紡がれた物語と、一貫した価値観が欠かせません。
ストーリーブランディングを通じて、共感から共鳴へ。
価格では語れない価値を持つブランドが、これからの時代、ますます選ばれていくことでしょう。
次回は、効果的なSNSキャンペーンの戦略についてお伝えします。
単なる販促で終わらせない、ファンとの距離を縮めるSNS活用のヒントを、一緒に探っていきましょう。
(アイキャッチ画像:Designed by Freepik)
WEB制作・ITに関するお悩みや
ご質問等お気軽にご相談ください