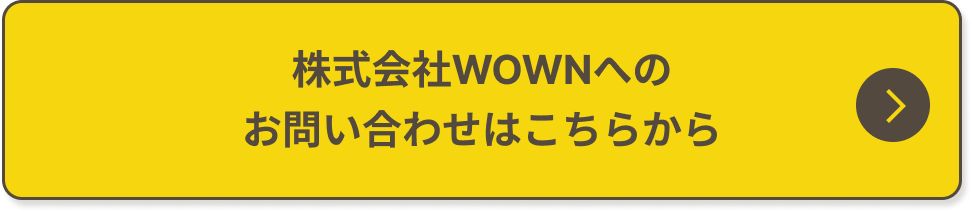「広告に頼らずに売上を伸ばすには?」「価格競争から抜け出すには?」
こうした問いに対する答えのひとつが、「ファンを育てること」です。
商品やサービスの魅力だけでなく、企業の想いや姿勢に共感し、応援してくれる“ファン”を獲得できれば、自然な形でブランドが広がっていきます。
今回は、実際にファンマーケティングで成功を収めた3つの企業の取り組みを紹介しながら、中小企業でも取り入れられる工夫を探っていきます。
目次
「第三の場所」でファンを魅了──スターバックス
スターバックス(https://www.starbucks.co.jp/)は、ファンマーケティングの代名詞とも言える存在です。誰もが知る大企業ですが、同社のマーケティング戦略には、中小企業でも取り入れられる要素が少なくありません。
スターバックスは、「人々の心を豊かで活力あるものにする」という理念のもと、日常に癒しや特別感を提供する体験型ブランドとしてファンを獲得してきました。
その象徴ともいえるのが、「第三の場所(Third Place)」というコンセプト。自宅でも職場でもない“もうひとつの居場所”として、バリスタとの気軽な対話や、自分好みにカスタマイズできるドリンクなどを通して、顧客が思い思いの楽しみ方ができる場を提供しています。さらに、店舗も地域の文化や建築に合わせた内装にするなど、「訪れる楽しさ」を演出している点も特徴です。
また、SNS活用にも非常に積極的です。公式アカウントでは、シーズナルドリンクの告知や新商品紹介を行うだけでなく、ユーザーとのコミュニケーションにも力を入れています。特にInstagramでは、ハッシュタグ「#スターバックス」「#フラペチーノ」などを通じて、ユーザーが自発的にスタバ体験を投稿する文化が形成されています。これは、いわば“ファンが広報を担う”仕組みとも言えるでしょう。
環境への取り組みもファンの共感を集める要素です。タンブラー割引によって顧客にタンブラーの持参を促す施策は、期間限定のタンブラー販売との相乗効果によって、広く認知されています。また、プラスチックストロー廃止の際には「紙ストローがふやける」といった不満の声もありましたが、理念に共感するファンは離れませんでした。のちにファンの声を受けて、生分解性プラスチックストローへの切り替えが行われたことも、スターバックスが顧客の声に真摯に耳を傾けている証と受け取られ、同社の評価を高める結果となりました。
スターバックスは、店舗・接客・商品・デジタル・社会貢献と、あらゆる接点で「共感・特別感・参加感」を提供しており、ファンとの関係性を軸にブランドを成長させています。
職人の想いでファンを惹きつける──木村石鹸工業(大阪府)
大阪の木村石鹸工業(https://www.kimurasoap.co.jp/)は、その名のとおり石鹸製造の老舗メーカー。伝統の「釜焚き」製法を絶やすことなく、職人の手作業による石鹸製造を続けています。長らくOEM製造を主としていましたが、近年は自社ブランドを立ち上げ、ファンマーケティングを実践しています。
同社が展開する、人にも環境にも優しい洗剤や石鹸の自社ブランド「SOMALI」や「12/JU-NI」は、「小さなメーカーだからこそ実現した、“正直な処方”」というコンセプトがユーザーに刺さり、丁寧な暮らしを志向する層に支持されています。
注目すべきは、現場の職人や開発者の声を積極的に発信している点です。ホームページでの開発コンセプトや想いの発信に加え、製造の過程やちょっとした工夫、香りへのこだわりなどをnoteやInstagramで紹介することで、消費者が「誰がどのように作っているか」を知り、その想いに共感する仕組みを作っています。
さらに、SNSやレビューから寄せられる顧客の声を製品改良に活かし、クラウドファンディングを活用する「共創」の姿勢も、ファンを育てる大きな要素といえるでしょう。“このブランドを一緒に育てている”という実感が、自然と応援したい気持ちを引き出す――そんな仕組みがうまく働いています。
レトルト食品への情熱が共感を呼ぶ──にしき食品(宮城県)
宮城県に本社を構えるにしき食品(https://nishikiya-shop.com/)は、カレーやパスタソースをはじめとしたレトルト食品のメーカーです。県内に直営店を展開するほか、直販サイトや各種ECサイトを通じて商品を販売しています(県外では東京・自由が丘に1店舗を構えるのみです)。
同社は地方に根ざした中小企業でありながら、ユニークなプロジェクトやファンマーケティングを通じて、全国に名を知られるメーカーへと成長を遂げています。
同社の強みは、レトルト食品であっても妥協のない品質と製法へのこだわり。保存料・化学調味料不使用を貫き、食材やスパイスも自社スタッフが試食を重ねながら厳選しています。ECサイトやSNSでは、その開発過程を丁寧に発信しており、透明性と誠実さが多くのファンを惹きつけています。
また、「#NISHIKIYAKITCHEN」などのハッシュタグがついたInstagram投稿をECサイトで紹介する施策も好評で、多くの投稿が集まっています。
中でも特に注目すべき取り組みのひとつが、「小学生の夢のカレー」プロジェクト。これは、味・価格・パッケージデザインまで、小学生と一緒に企画・開発を行い、商品化するというもの。「創造力を育むと同時に、ものづくりの楽しさ・喜びを知る一生ものの体験をしてほしい」という同社の想いがこもった活動です。このプロジェクトはメディアでも取り上げられており、理想的なファンマーケティングの一例といえるでしょう。
ほかにも、工場見学などオフラインでの取り組みも活発で、単なる商品購入にとどまらない顧客との継続的な関係性を築いています。
中小企業こそ効果あり!ファンづくりのヒント
3社の事例に共通するのは、「共感されるストーリーの発信」と「顧客と対話する姿勢」です。ファンマーケティングとは、作り手の姿が見え、企業が顧客の声をしっかりと受け止める仕組みを作り、両者のつながりを深めていくことに他なりません。
以下に、中小企業が取り入れやすいファンマーケティングの取り組み例をまとめました。予算が限られていても、小さな一歩から始められることが、ファンマーケティングの大きな魅力です。
- ブランドの背景を発信する
なぜこの商品を作ったのか、誰が作っているのか、開発者の想いを伝える - SNSで顧客の声を拾う
レビューやコメントに返信し、声を製品改善に活かす - 顧客を巻き込む
商品開発のアイデア募集、投稿キャンペーンなどを実施する - 特別な体験を提供する
工場見学、限定商品、ストーリーのある企画などで関係性を強化する
まとめ
ファンマーケティングは、大企業だけの戦略ではありません。中小企業だからこそできる、等身大のストーリーや現場感のある発信は、顧客の共感を得やすく、長く愛されるブランドづくりにつながります。
スターバックスのような“体験設計”、木村石鹸のような“想いの発信”、にしき食品のような“共創の姿勢”——これらは、企業の規模を問わず実践可能な手法です。
広告に頼らない持続的な成長を目指すなら、まずはお客様との「つながり」を深めるところから始めてみてはいかがでしょうか。
次回は、「ファンを育てるSNS活用術」にフォーカスします。InstagramやLINE、noteなどを活用して顧客との距離を縮める方法や、実際の投稿企画・UGC活用事例を交えながら、明日から実践できるヒントをご紹介予定です。
(アイキャッチ画像:Designed by Freepik)
WEB制作・ITに関するお悩みや
ご質問等お気軽にご相談ください