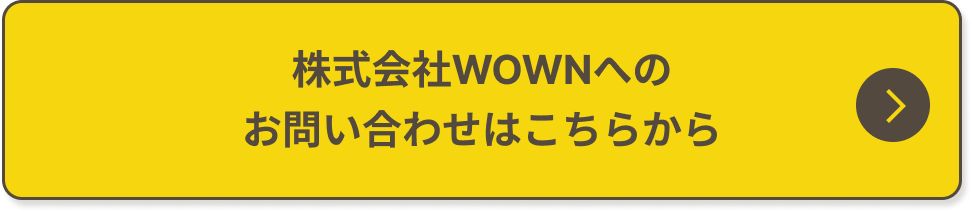かつて、商品やサービスは企業が企画・開発を行い、完成品として顧客に提供するのが当たり前でした。
しかし、SNSやクラウドファンディング、オンラインコミュニティといった「つながりの場」が多様化した今、その構図は大きく変わりつつあります。
商品やサービスは「企業が作るもの」から、「ファンと一緒に育てるもの」へと変化しています。
企業とファンが価値観を共有しながら、“共感”を“共創”へと進化させていくことが、これからのブランドづくりの鍵となるでしょう。
本記事では、実際にファンの声を商品開発に取り入れている中小企業の事例を紹介しながら、共創的なマーケティングを実践するための考え方と仕組みづくりのヒントをお届けします。
目次
ファンと「一緒につくる」とは?──共創マーケティングの基本
共創マーケティングとは、企業と顧客が協力しながら、新たな価値を創造していくマーケティング手法です。企業がファンの声に耳を傾けるだけではなく、開発や運営の“プロセス”に積極的にファンを巻き込むことで、より深い関係性を築きながら商品やブランドを成長させていきます。
商品開発におけるファンの役割は「同志」
ファンは単なる「消費者」ではなく、企業の価値観や理念に共感し、応援してくれる存在。さらに共創の場において、ファンは「一緒にブランドを育てる同志」となります。
この「同志感」は、単なるアンケート調査やモニターの枠には収まりません。ファン自身の体験や想いが商品に反映されることで、ブランドへの愛着やロイヤルティを深めてくれるものです。
「声を聞く」から「一緒にプロセスを歩む」へ
共創の鍵となるのは、ファンにただ意見を聞くだけでなく、商品開発やサービス設計、プロモーション活動など、さまざまなプロセスに「参加」してもらうことです。
たとえば、
- 素材やパッケージの選定に意見をもらう
- 試作品を先行体験してもらい、フィードバックを受ける
- SNSで開発ストーリーを発信し、開発者の苦労やワクワク感を共有するとともに、ファンの要望を取り入れる
こういった取り組みは、ファンの“当事者意識”を生み出すと同時に、「一緒につくった」という達成感をもたらします。結果として、長期的な関係の構築にもつながるのです。
ファン同士の交流の場をつくる
ファン同士がつながり、語り合える環境を用意することも、共創を促進する重要な要素です。
「好きなことを語り合いたい」という気持ちは、誰もが持つ自然な欲求。読書記録アプリ、写真投稿サイト、コスメレビューコミュニティなどが活発なのは、この心理に基づいています。
企業がファン同士の交流の場を設けることで、ファンコミュニティの熱量が高まり、そこから新たな商品アイデアやニーズが自然発生的に生まれてくる可能性もあります。そして何より、そうした場を通じて「自分たちはブランドにとって大切な存在だ」とファンが実感できることが、関係構築の土台になります。
中小企業でも始められる“小さな共創”の設計とは?
「共創」という言葉を聞くと、大掛かりなプロジェクトや仕組みを想像するかもしれませんが、実際にはもっと小さな取り組みからでも始められます。
たとえば、
- 購入時のアンケートやSNSでのコメントを丁寧に拾い上げる
- 小さな改良点をファンにフィードバックする
- ブログで開発の裏側を発信する
といった日々のやりとりの積み重ねが、ファンのロイヤルティを確実に高めていくのです。
自分の声が企業に届いて意見が反映された。あるいは、丁寧に対応してもらえた。
こうした小さな感動体験こそ、ファンの心を動かし、「このブランドを応援したい」という気持ちを育てていくのです。
PLUS MANIA(プラスマニア)|“ふだんピング”に共感したファンと一緒に育てる
PLUS MANIAは、新潟県にある金属加工の老舗「工房アイザワ」が展開するアウトドアブランド。創業から90年以上続く金属製品の技術力をベースに、現代のライフスタイルに寄り添う新しい製品をファンとともに生み出しています。
ブランド立ち上げのきっかけは、開発担当者の「ベランダ飲み」という個人的な体験。そこから生まれた「ふだんピング(=日常にアウトドア気分を持ち込む)」というコンセプトは、多くの共感を呼びました。
- 日常でも使えるアウトドアギアで「ふだんピング」の共感軸
- クラウドファンディングでファンのニーズを“製品化”に反映
- Instagramなどでの丁寧な世界観づくりと、製品開発のプロセス共有
- 「自分もふだんピングしたい」と思わせるレシピや活用法の発信
キャンドル用の五徳can+ro(キャンロ)やポータブル暖炉DAN+RO(ダンロ)は、クラウドファンディングで達成率500%という快挙を達成。「こんな製品が欲しかった」というファンの声に耳を傾けながら、共感から共創へと着実に歩みを進めている好例です。
久世福商店|コミュニティでファンとつながる
日本全国の「うまいもの」を集め、日本の食文化の素晴らしさを発信する「ザ・ジャパニーズ・グルメストア」をコンセプトに全国展開する久世福商店。創業の原点は、長野県で営まれていた小さなペンションにあります。そこで提供されていたオーナー夫人の手作りジャムが人気を呼び、商品販売へと発展しました。
同社は、ファンとのつながりを強化するために「福の会・ぶどうの会」というクローズドコミュニティを運営。ここでは、
- ファン同士の交流
- アンケートやイベントの告知
- 開発中商品の情報共有
- レシピや食の提案
といった活動が行われており、これらの活動を通じて、実際に寄せられた声が商品開発や改良に反映されています。
- ブランドストーリーやレシピの共有によって、共感軸を形成する
- クローズドな場でファン同士の関係性を醸成
- 双方向のやりとりがブランドへの信頼感を生む
ファンとのつながりを大切にしたコミュニティ運営は、ファンマーケティングの教科書のような実践といえるでしょう。
シルクふぁみりぃ|1対1の対話を商品に反映
敏感肌の創業者が、地元奈良県の靴下に感動したことから始まったシルクふぁみりぃ。現在は、天然素材を中心にしたインナーやソックスを展開する小さな会社です。
最大の特長は、ユーザーの声に対する“誠実な対話”。問い合わせや備考欄に記された小さなコメントにも、丁寧に電話やメールで対応する姿勢は、多くのファンの心を掴んでいます。
- 店主ブログによる開発の共有とユーザー参加の余地
- 「合う商品を一緒に探しましょう」と顧客に寄り添う姿勢
- 小さな声を丁寧に拾って、商品開発や対応に活かす
たとえば、「これが肌に合わなかった」と書いたユーザーに対し、「急がなくていいんですよ。本当に合うものを一緒に探しましょう」と優しく寄り添う姿勢に、感動したファンは少なくありません。
商品にストーリーがあるのではなく、関係のなかで“物語が育つ”──そんな温かさを感じさせる、共創のひとつの形です。
共創マーケティング成功の4ステップ
1. 声を拾う場をつくる
ブログ・SNS・アンケート・クラウドファンディングなど、ファンが声を発しやすい「入り口」を整える。
2. プロセスを公開する
開発途中の段階からこまめに情報を共有し、ファンにプロセスを見てもらう。進行中の様子を伝えることで関心と信頼が高まる。
3. ユーザーの声を反映し、伝える
「こんな意見があったので、こう変更しました」と背景とともに伝えることで、ファンの“自分ごと感”が増す。
4. 同志になってもらう
ブランドの想いや共感軸を共有し、「一緒に育てる空気」をつくる。
まとめ:ファンは“完成品”ではなく“過程”でできあがる
共創マーケティングの本質は、完成した商品そのものよりも「一緒につくるプロセス」にあります。商品開発に関わり、自分の声が届いたという実感を得たファンは、ブランドへの愛着をより深めていくものです。
そして、こうした“対話型の関係構築”こそ、中小企業が持つ最大の強みでもあります。大規模な仕組みでなくても、日々の小さな声に耳を傾けることで、信頼と共感は着実に育っていきます。
次回は、ファンの共感を“共鳴”へと進化させる「ストーリーブランディング」についてご紹介します。推したくなるブランドとは何か? ファンの心を動かす物語設計の方法に迫ります。
(アイキャッチ画像:Designed by Freepik)
WEB制作・ITに関するお悩みや
ご質問等お気軽にご相談ください