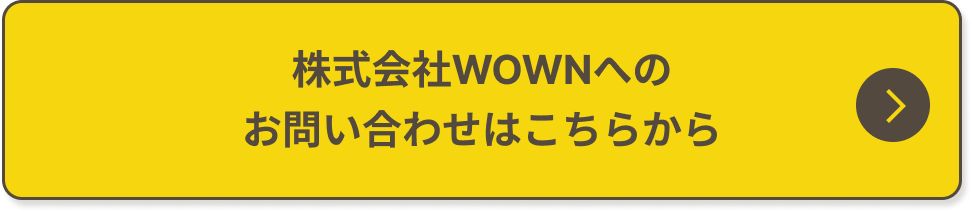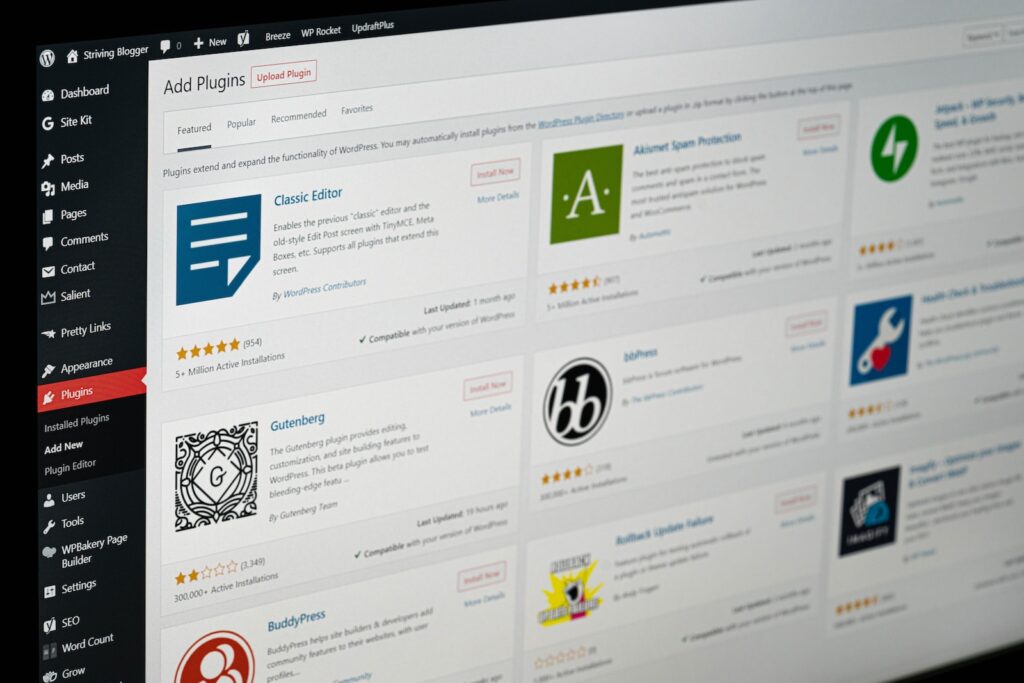SNSを活用して企業の魅力を伝えたい。だけど「ファン」との関係性を深めるために、なにを、どう発信すればいいのかわからない。SNSを運用するにあたって、そのような悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
本記事では、SNSを通じて企業と顧客が“ちょうどよい距離感”でつながるためのヒントを、「中の人」の存在に注目してご紹介します。特に、限られたリソースの中でも親しみと信頼を育んでいきたいと考える、中小企業の運用担当者の視点でまとめています。
この記事が、SNS運用における迷いや不安を解消する一助となれば幸いです。
なんのためにSNSを運用するのか?
SNSは、継続してこそ価値が発揮されるもの。最初から飛ばしすぎず、細く長く続けること、そしてキャラクターをぶらさないことが大切です。そのためにも、まずはSNS運用の“目的”を明確にしておくことが重要です。目的が定まっていれば、“中の人”の投稿内容やトーンにも一貫性が生まれ、ファンとの信頼関係を築きやすくなります。
- 企業のイメージアップ・ブランディング強化
まずは企業の存在を知ってもらうことが、スタート地点となります。ただし、むやみに投稿を重ねるだけでは逆効果となることも。投稿のトーンや方向性には統一感を持たせることが重要です。 - ファンとの接点・交流(エンゲージメント)の強化
SNSは双方向のメディアです。誰に届けたいのかというターゲット像(ペルソナ)を明確にすることで、関係性を深めていくことができます。年齢層や性別、職業、ライフスタイルなどを想定し、投稿内容を調整していくと良いでしょう。 - サービスや商品の認知度アップ
広告では発信しにくいニッチな活用シーンや意外な使い方を紹介することで、既存ファンとの関係が深まるだけでなく、新たなファン層へのアプローチにもつながります。 - 購買意欲の向上・イベント・キャンペーン告知
タイムリーな投稿で購入を後押ししたり、イベントやキャンペーンの参加を促したりと、フォロワーの行動を引き出す設計も欠かせません。
なぜ“中の人”が注目されるのか?
最近では、企業アカウントにも「人間味」が求められるようになってきました。たとえば「パインアメのパイン株式会社」や「シュークリーム先輩(モンテール公式)」に見られるユニークな投稿は、“中の人”の個性が前面に出ることで、フォロワーとの距離を縮めています。
“推されるブランド”には人格がある——。これは第6回で取り上げたストーリーブランディングにも通じる考え方です。企業と顧客という関係を超えて、人と人との関係性として信頼を築くことが、今のSNS運用における大きなテーマとなっています。
ターゲットのペルソナを設定するのと同じくらい、ブランド=“中の人”の人格をぶらさないことが重要であるという点は、ぜひ押さえておきたいポイントです。
顔出しナシでも「人が見える発信」の工夫
“中の人”が必ずしも顔出しをしているとは限りません。実際、多くの企業アカウントでは顔出しなしで運用されています。それでも、「誰かが運用している」という実感が伝わる投稿には親しみが生まれます。
- キャラクターを立てる
トーンに一貫性を持たせ、絵文字や特徴的な語尾を効果的に使うのもおすすめです。たとえば、ぼんち揚公式ぼんち猫のXでは「〜するに゛ゃ」という語尾が印象的です。複数人で運用していても、語尾や言い回しを統一することで“なりきり感”が生まれ、雰囲気を揃えることができます。 - マスコットキャラクターの活用
中の人=キャラクターという戦略は、リソースの限られる中小企業にとっても非常に有効です。たとえばミツカンの公式Xでは、「ぽん酢たち」というキャラクターが投稿の語り手となっており、親しみやすさと情報発信の一貫性を両立しています。Instagramで人気の“ぬい撮り”文化を活用し、旅先や日常の風景とキャラを絡めた投稿は、ファン化を促す好例です。 - ユニークな外見・語り口の中の人
モンテールの「シュークリーム先輩」は、シュークリーム型の被り物とフレンドリーな語り口で多くのファンを獲得しています。ユニークさと親しみやすさを両立した好例です。 - イラストや手書き文字の活用
4コマ漫画やアスキーアートなど、視覚的に「らしさ」が感じられる投稿は、強い印象を残します。キングジムのように、曜日ネタを定番化するのも一つの手です。 - オフィスの風景や日常写真の投稿
キングジム公式では、商品名の由来や開発エピソードなど、仕事の裏側が垣間見える投稿を行なっています。顔を出さずとも「人となり」は十分に伝えられます。
スタッフ紹介・裏側投稿で育てる共感と信頼
製品紹介やキャンペーン情報の投稿はもちろん大切ですが、「売ること」ばかりに偏りすぎると、ファン離れを引き起こすリスクもあります。SNSにできて広告にはできないこと、それがエンゲージメントの強化です。
中の人が語る裏話や制作日記、業務中のこぼれ話などの投稿は、共感や信頼を育む材料になります。社員紹介では、ただのプロフィールではなく、「どんな人か」「どんな想いで働いているか」を伝える視点が重要です。
また、コメントへの丁寧な返信や、UGC(User Generated Content)のリポストなど、ファンとの双方向コミュニケーションも、距離を縮める有効な手段です。
雑談力がファンを生む:製品と関係ない話が信頼につながる
企業アカウントにもかかわらず、製品とは直接関係のない「雑談」でファンを獲得している例もあります。
たとえば、ナイセンの「おやつの時間」や「出勤報告」といった日常の投稿は、バズを狙うものではありませんが、一定のファン層に親しまれています。
こうした定番の“雑談テーマ”をあらかじめ設定しておくと、投稿の継続やネタ出しも楽になります。
製品紹介ばかりでなく、日常のちょっとした投稿を織り交ぜることで、企業の雰囲気やカルチャーが、より身近に感じられるようになります。
中の人がブランドそのものに──シャープの象徴的な事例
ここまで、“中の人”のキャラづくりがいかに重要かを見てきましたが、その存在がブランドそのものとして定着した事例もあります。
その象徴的な例が、シャープの公式アカウントです。
“中の人”である山本氏が退職後も、企業が委託という形でSNS運用を継続した背景には、キャラクターをブランドの一部と認識していた企業側の判断がありました。
「人」を起点にブランドを設計し、守ることは、企業の大きな資産にもなり得るという好例です。
炎上しない距離の取り方と対応マナー
距離が近いSNSだからこそ、言葉選びや対応には細心の注意が求められます。
親しみやすさを演出したつもりが、過度な内輪ノリや自虐ネタにより、フォロワーとの間に温度差が生まれてしまうことも。
また、政治・宗教などセンシティブな話題には慎重な姿勢が必要です。
炎上リスクを避けるためにも、あらかじめ企業のスタンスや投稿方針をガイドラインとしてまとめておくことが大切です。
投稿が軌道に乗るまでは、複数人での確認体制を整えると安心です。
まとめ
企業アカウントの理想形は、単なる情報発信ツールにとどまらず、「人」として信頼される存在になることです。
“中の人”の存在は、共感を生み、ファン化を促す大きな要因となります。
雑談や裏話、日常の発信といったやり取りを通じて、ファンの“参加意識”と“共感”を高め、ちょうどよい距離感を築いていくことが、これからのSNS運用においてますます重要になるでしょう。
企業アカウントであっても、結局は人と人。「人間味」が伝わる投稿で、ファンの心を掴みましょう。
次回は、“オフラインでファンとのリアルな接点をどうつくるか?”をテーマにお届けする予定です。
(アイキャッチ画像:Designed by Freepik)
WEB制作・ITに関するお悩みや
ご質問等お気軽にご相談ください